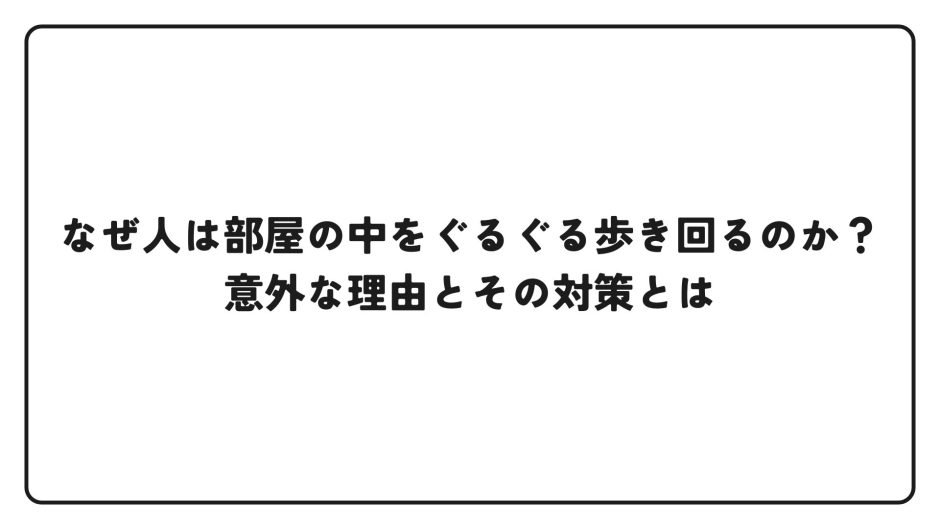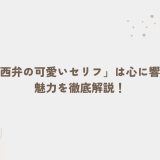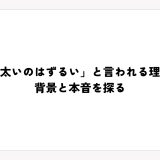「部屋の中をぐるぐる歩き回る姿を見て、どう対応すればいいのかわからない」——そんな戸惑いを感じたことはありませんか?何度も歩き回る様子に不安やイライラを覚えるのは、介護する側として自然な感情です。
本記事では、「なぜぐるぐる歩くのか?」という行動の背景にある心身の要因を、認知症や心理面など多角的に解説します。
目次
- 1. はじめに:部屋の中をぐるぐる歩き回る姿に、戸惑うあなたへ
- 2. そもそも「ぐるぐる歩き回る」ってどんな行動?
- 3. 【主な原因】認知症・身体・心理の3つの視点から分析
- 4. 【チェックリスト】ぐるぐる歩く人に当てはまるかもしれない行動兆候
- 5. 【対応の考え方】無理に止めようとせず、“理由”を探ることから
- 6. 【具体的な対策】ぐるぐる歩きの5つの解消アプローチ
- 7. 【環境づくり】歩きたくなるのは自然、ならば“安心して歩ける”空間に
- 8. 【ケーススタディ】現場で実際にうまくいった工夫例
- 9. 【介護者の心を守る】自分の余裕がケアの質を左右する
- 10. 【さらに深く学ぶ】症状を“理解する力”が、家族を救う
- 11. おわりに:「ぐるぐる歩く」その姿の奥にある“想い”に寄り添って
1. はじめに:部屋の中をぐるぐる歩き回る姿に、戸惑うあなたへ
介護の現場でよく見かける光景の一つが、部屋の中をぐるぐる歩き回る高齢者の姿です。
とくに認知症を患っているご家族がこのような行動を繰り返すと、「何してるの?」「何がしたいの?」と、どうしても問いかけたくなります。
けれど、その問いにはっきりとした答えが返ってくることは少なく、結果的にまた同じように歩き回るということが繰り返されてしまうのです。
このような行動に、どう対応すればよいか分からず戸惑う方は非常に多いです。
もしかすると、あなたも毎日の介護に追われながら「なぜこんな行動をするのだろう」と悩んでいませんか。
ここでは、「部屋の中をぐるぐる歩き回る」という行動の背景と、それに対する介護者の自然な感情について丁寧に見ていきます。
1.1 「何してるの?」に答えず、また歩く
「お母さん、さっきもそこ通ったよね?」
「用がないなら、ちょっと休んでてよ」
こんな声をかけたこと、ありませんか。
けれど、それに対して本人は「うん」とうなずくだけで、しばらくするとまた歩き始める──。
何か目的があって動いているようには見えず、ただただ家の中を行ったり来たりする姿に、介護者としては心配と同時に、理解しがたいもどかしさを感じることがあるかもしれません。
実際、これは認知症の方に非常によく見られる行動の一つで、「徘徊」とも呼ばれています。
この行動の背景には、身体的不調(たとえばトイレの問題や痛み)が隠れていることもあれば、「何かしなきゃ」という焦燥感がある場合もあります。
しかしながら、本人にとってもその理由を言葉にして説明するのは難しいのです。
ですから、問いかけても答えが返ってこず、また歩き出す──という状況が生まれます。
大切なのは、その行動には必ず理由があるという視点を忘れずに持つことです。
1.2 イライラしてしまう介護者の本音も自然な反応
「目が離せないから家事も進まない」「じっとしていてくれたらどれだけ楽か」──。
そう思ってしまうのは、とても自然な感情です。
どんなに愛する家族であっても、毎日同じような行動を繰り返されれば、ストレスは溜まって当然です。
実際、認知症の家族と暮らす介護者の多くが、このような「イライラ」との向き合い方に苦労しています。
あるケースでは、同居している母親が毎日家の中を落ち着きなく歩き回り、目が離せない状況に。
家事も中断されがちで、結果的に「見るだけでイライラしてしまう」という気持ちにまでなってしまったといいます。
けれど、この「イライラ」はあなたの心が弱いからでも、愛情が足りないからでもありません。
行動の意味が分からない、目的が見えない、止めさせる術がない──この無力感や混乱が、怒りに変わるのです。
ですからまずは、自分の感情を否定しないことが大切です。
「イライラして当然」と自分に言い聞かせていいのです。
そのうえで、少しずつ行動の背景を探っていくことで、本人の不安も、介護者自身の気持ちも和らげることができるでしょう。
2. そもそも「ぐるぐる歩き回る」ってどんな行動?
家の中を何度も行ったり来たり、まるで目的もなくぐるぐる歩き回る姿を見ると、「一体なにをしているんだろう?」と感じてしまうことはありませんか。
特に、認知症の方と暮らしていると、「じっと座っていればいいのに」「用がないのに、どうして歩き回るの?」と疑問に思ったり、時にはイライラしてしまうこともあるでしょう。
でも実は、この「ぐるぐる歩き回る」という行動には、見えにくいけれど確かな理由があることが多いのです。
このセクションでは、そんな「歩き回る行動」の種類や、それに似た他の行動も含めて、詳しくご紹介していきます。
2-1. 目的のある徘徊と、無目的な反復行動の違い
まず大事なのは、「ぐるぐる歩く」という行動にも種類があるということです。
目的がある徘徊というのは、たとえば「トイレを探している」「誰かを探している」「何かを思い出そうとしている」など、本人なりに目的意識があって動いている行動です。
実際、認知症の方の中には、「洗濯物を干そうとしていたけど、途中で忘れてしまって、それでも身体だけが動き続けてしまう」というようなケースもあります。
一方で、無目的な反復行動とは、何かをしようとする気持ちすら曖昧で、ただ身体が反射的に動いてしまうような状態です。
これは、認知症によって「今なにをするべきか」を判断する力が低下している場合に見られます。
たとえば、記憶があいまいで何かやらなきゃと思っているけど、何をすればいいのかがわからない。そのような時、脳が命令を出せず、ただただ歩き回ってしまうという行動につながるのです。
この違いを理解すると、「うろうろしないで」と止めるのではなく、まずは理由を探ってみようという気持ちに変わるのではないでしょうか。
2-2. 似たような行動:立ち上がっては座る、家の中を行ったり来たりする
「ぐるぐる歩き回る」行動に似ているものとして、「立ち上がってはすぐ座る」「何度も同じ場所を往復する」といった行動もあります。
これらもやはり、認知症にともなう行動の一つと考えられます。
例えば、椅子から立ち上がったと思ったらすぐに座る。これを何度も繰り返す場合、「トイレに行きたいけど、場所がわからない」「何かしようとしているけど忘れてしまった」という背景があることも。
また、家の中を何度も往復して歩く行動も、「何かを探している」「目的地が思い出せない」という意識の表れかもしれません。
このような行動には、本人も自分の中で混乱しているという事情が隠れていることが多いのです。
無意識のうちに不安を感じていたり、身体が落ち着かない感覚を和らげようとして、同じ動きを繰り返すというケースもあります。
つまり、すべての行動には何らかの原因があるという前提で見守ることが、本人にとっても介護者にとっても、大きな安心につながるのです。
2-3. まとめ
「ぐるぐる歩き回る」「立ったり座ったりを繰り返す」「家の中を行ったり来たりする」。一見、目的がないように見えるこれらの行動も、実は本人なりの理由や背景があるということがわかります。
それが「不安」だったり「忘れてしまった使命感」だったり、「身体を動かさずにはいられない違和感」だったりするのです。
こうした行動を目にしたとき、頭ごなしに「座ってなさい」と言っても根本的な解決にはなりません。
まずは行動の目的を探ってみること。そして、可能であれば、その目的に寄り添う工夫をすること。
それが、ぐるぐる歩き回る行動と上手につき合っていくための第一歩になります。
介護をするご家族の方にとっても、「理由がある」と理解できれば、気持ちの負担がぐっと軽くなるかもしれません。
3. 【主な原因】認知症・身体・心理の3つの視点から分析
3-1. 認知症に特有の「目的探索行動」
認知症の方が部屋の中をぐるぐる歩き回る理由として、まず考えられるのが「目的探索行動」です。これは、自分自身でもはっきりとは認識できない「何かを探している」状態です。例えば、「トイレに行きたい」「大切な物を探している」「どこかへ行かなきゃ」といった漠然とした思いが背景にあります。ただ、認知機能の低下により何を探しているのかが途中で分からなくなってしまうことがよくあります。
また、本人は「目的がある」と感じているため、声をかけても納得できず、歩き回る行動を続けてしまうことがあります。これは認知症の中でもアルツハイマー型認知症の方によく見られ、特に夕方以降に頻度が増す「夕暮れ症候群」の一環としても起きやすいです。このような時は、「何か探しているのかな? 一緒に探してみようか?」と本人の気持ちに寄り添った対応を心がけると、行動が落ち着く場合があります。
3-2. 身体的不快(トイレ、痛み、脱水、便秘など)
人は身体に不快感があると、自然と落ち着かなくなります。認知症の方も例外ではありません。「なんとなく気持ち悪い」「どこかが痛い」「トイレに行きたいのにうまく伝えられない」といった状態が、ぐるぐる歩き回る行動につながることがあります。
とくに便秘や尿意など、違和感があってもそれを言葉にできない場合、本人にとっては非常に不安です。実際、介護の現場では「歩き回っていた方が排泄後に落ち着いた」というケースもよく見られます。また、脱水による脳機能の一時的な低下も落ち着きのなさに拍車をかけるため、日々の水分補給も重要です。
このような場合には、体調チェックと生活リズムの見直しが効果的です。お腹の調子や排泄の間隔、水分摂取量などを観察し、気づいた変化には早めに対応しましょう。
3-3. 日課や記憶の反復(昔の生活習慣を再現しようとしている)
認知症の方は、昔の記憶を鮮明に覚えていることがあります。そのため、若い頃に毎日行っていた日課、たとえば「掃除をするために歩き回る」「出勤しようとして玄関を探す」といった行動が無意識のうちに再現されることがあるのです。
あるお母さんは、毎朝ご飯を作っていた頃の記憶が残っていて、「台所で何かしなければ」と感じていたようです。今ではその必要がなくなったにもかかわらず、体が自然に動いてしまい、結果として部屋を歩き回ることに繋がっていました。
このような場合は、本人の過去の生活背景を理解することが非常に役立ちます。また、「○○さん、今日は一緒にこのお皿拭いてもらえる?」など、役割を与えて安心感を持ってもらう工夫も効果的です。
3-4. 精神的不安(不安感、孤独感、環境への混乱)
認知症の方が室内を歩き回る行動には、精神的な不安や孤独感が隠れていることもあります。見知らぬ場所にいるような感覚に襲われたり、「ここは自分の家じゃない」と思い込んだりするケースもあります。また、同居家族の様子が変わっただけでも混乱して不安を強め、居場所を求めて歩き続けることがあるのです。
さらに、「なぜ歩いているのか?」と問われたり、行動を制止されたりすると、本人は自分を否定されたような気持ちになってしまいます。その結果、かえって不安が強くなり、落ち着きがなくなるという悪循環に陥ることもあります。
不安が原因であると感じたときは、まずは「話を聴いてあげる姿勢」が大切です。「一緒にここで座ろうか」と優しく寄り添い、安心できる環境を整えていくことが、行動の改善に繋がります。
3-5. 刺激不足や退屈からくる「なんとなく歩く」状態
毎日同じ環境で、特にやることもなく過ごしていると、誰でも退屈になってしまいますよね。認知症の方も同じで、「なんとなく手持ち無沙汰」「何をしたらいいのかわからない」といった状態になると、ただただ歩き回ることがあります。
「用事があるわけじゃないのに、ずっと歩いてる…」という状態は、刺激不足によるものかもしれません。趣味や簡単な作業、音楽、折り紙、塗り絵などの軽い活動を取り入れることで、気持ちの切り替えができ、無目的な歩行が減る可能性があります。
一人でじっとしている時間が長くなると、気分も塞ぎ込みがちになるため、「やることがある状態」をつくることが大切です。
3-6. 内服薬の影響で落ち着かないこともある
意外と見落とされがちですが、薬の副作用も認知症の方の「ぐるぐる歩き回る」行動に影響を与えることがあります。たとえば、睡眠薬や抗精神病薬、利尿剤などの影響で、夜中に目が覚めて不安になったり、トイレを頻繁に探しに行ったりすることも。
特に新しい薬を処方された直後や、用量が変わった時期は注意が必要です。「最近になって急に落ち着きがなくなった」と感じたときは、服用中の薬について医師や薬剤師に相談してみましょう。
副作用による落ち着きのなさは、投薬内容の調整によって改善できる場合もあります。周囲の環境や行動だけでなく、薬の影響にも目を向けることが大切です。
4. 【チェックリスト】ぐるぐる歩く人に当てはまるかもしれない行動兆候
認知症の方が家の中をぐるぐる歩き回る行動は、単なる“徘徊”として片づけてしまうにはもったいないほど、深い理由が隠れていることがあります。このチェックリストでは、そうした行動の裏にある兆候やサインに目を向け、介護者が適切に対応するためのヒントを紹介します。行動そのものを「やめさせる」のではなく、「なぜそうしているのか?」に焦点を当てることが大切です。
4-1. 最近転倒やケガはないか?
まず最初に確認したいのは身体の異変です。本人が訴えなくても、足元の痛み、股関節の違和感、あるいは過去の転倒の記憶から来る不安などが原因で、落ち着かずに歩き回っていることがあります。特に、大腿骨頸部骨折の既往歴がある高齢者や、骨粗しょう症の診断を受けている方では、慎重な歩行を繰り返す様子が見られることも。また、靴やスリッパが合っていないことが原因で、足が痛くなり、何度も動いて位置を変えている可能性もあります。歩き方に違和感を感じたら、専門医に相談することも考えましょう。
4-2. 食事・排泄のタイミングに乱れは?
ぐるぐる歩く行動の背景には、生活リズムの乱れが隠れていることもあります。「トイレに行きたいけど、場所を忘れてしまった」「お腹が空いているけど、どう伝えたらいいかわからない」など、身体からのサインを行動で表現している場合があるのです。
特に、便秘や尿意の我慢は、強い不安や落ち着かなさを引き起こします。このような場合は、食事と排泄の時間を毎日同じに整えることで、安心感を与えられる場合があります。また、排泄の直前に歩き回る傾向がないか、記録をとることも重要です。
4-3. 夜間にも同じような行動があるか?
日中の行動と夜間の行動を切り分けて観察することも大切です。夜間に同じように部屋をうろうろしている場合、昼夜逆転やせん妄(夜間せん妄)といった症状が疑われます。夜に十分な睡眠が取れていないと、昼間の活動が鈍くなり、結果として夕方以降に活動が増える「サンセット症候群」が見られることもあります。
このようなケースでは、日中の適度な運動や光を浴びる習慣が改善のカギになります。また、寝室の環境(暗さ、音、室温)も落ち着きを左右するため、細かく整えることが推奨されます。
4-4. どんな時に歩き出すか(時間帯・声かけ・環境)を記録してみる
ぐるぐる歩くタイミングを「いつ」「どんなきっかけで」始まるのかを、できるだけ詳しく記録することが重要です。たとえば、「午後3時頃、テレビが消えた直後に歩き出した」「家族が買い物に出るときに落ち着かなくなる」といった具体的な状況があれば、環境や心理的な要因が影響している可能性が考えられます。
認知症の方は、周囲の音や人の動きに過敏に反応することがあります。特に、介護者の声かけのタイミングや言葉選びによって、不安が高まり、歩き出してしまうこともあるため、日記のように記録することでパターンが見えてきます。
記録の例としては以下のような形が役立ちます: 記録することで、原因と対応策が結びつきやすくなります。介護を受ける本人の安心感、そして介護する側のストレス軽減にもつながる大切なステップです。
5. 【対応の考え方】無理に止めようとせず、“理由”を探ることから
認知症の方が家の中を何度もぐるぐる歩き回る光景に、つい「座っていてほしい」と思ってしまうのは当然のことです。介護者としても、家事や休息の時間が削られるため、心身ともに疲弊しやすくなります。ですが、このような行動を無理に止めることは、かえって逆効果になることが多いのです。なぜなら、その行動には必ず「理由」や「意味」が隠れているからです。
たとえば、ある女性は認知症のお母さんが家の中を行ったり来たりする様子に、つい「何してるの?」「座ってて」と声をかけてしまっていました。返事はしても、すぐにまた動き出す――その繰り返しにイライラが募ってしまっていたのです。けれども、そこで「どうしてこんなに歩き回るのか?」という視点に立ったとき、初めて気づけることがあります。
5-1. 行動の「意味」を考えるだけでイライラが減る理由
人は意味がわからない行動を見ると、不安になります。とくに、認知症の方が「目的なくうろうろしている」ように見えると、介護する側は「なぜ?」「やめてほしい」と感じてしまいます。けれども、かつては家事や育児で忙しく動いていたお母さんが、いま何もせず座っているという状況のほうが、本人にとってはむしろ「落ち着かない状態」なのかもしれません。
例えば、認知症の方が歩き回る理由として、以下のようなものが挙げられます。
- トイレに行きたい、あるいは体のどこかが痛いなど、身体的不調
- 何か用事をしようとしているが、内容を忘れてしまった行動の迷い
- 「何かをしなければ」という気持ちだけが先に立ち、具体的な行動がわからない認知的混乱
このような背景があると理解できれば、「ただのうろうろ」ではなく、「理由のある行動」だと受け止められるようになります。その結果として、介護者のイライラは自然と軽減されていくのです。
5-2. 介護者自身が「納得」することの重要性
認知症の方の行動に対して、介護者がどう受け止めるかは、日々のケアの質に大きな影響を与えます。「なんで止まらないの?」「何をしているの?」という疑問が怒りに変わる前に、まずは納得できる理由を探すことがとても重要です。
納得ができれば、たとえ状況が変わらなくても、自分の中に冷静さを保つことができます。そしてその冷静さが、優しさや寄り添いの気持ちを取り戻すきっかけになります。
たとえば、トイレの不安があった場合には定期的に促す、何か探し物をしているようなら一緒に確認する、役割を求めているようなら洗濯物をたたんでもらうなど、「納得」をもとにした具体的な行動がとれるようになります。
納得することは、介護の負担を減らすうえでも、非常に有効な心構えです。
5-3. “止める”のではなく“付き合う”発想への転換
どうしても「やめさせる」ことばかりに目が向いてしまいがちですが、それではお互いにストレスが増す一方です。「止める」よりも「付き合う」ことを考える、この発想の転換が認知症介護には求められます。
たとえば、あまりにも目が離せず介護者の疲労が限界に達している場合は、一時的に距離をとる選択も大切です。デイサービスを利用してもらう、あるいは介護者自身が買い物に出てリフレッシュするなど、「見えない状態」を作るだけで心の余裕が生まれます。
また、日常の中に「一緒に歩く時間」や「役割を与える場面」を設けることで、うろうろ行動は「危険な迷い」から「意味のある時間」に変わります。介護者の視点を切り替えることで、認知症の方との関係性も柔らかく、前向きなものになっていくのです。
5-4 まとめ
認知症の方が部屋の中をぐるぐる歩き回る行動には、必ず理由があります。その理由を探ろうとする姿勢が、介護者のイライラを減らし、より良い関係性を築く第一歩です。
止めようとするのではなく、行動の背景を知り、共に過ごす時間をどう工夫するかを考えていくことが、ストレスを減らす近道です。時には外部のサポートも取り入れながら、無理のない介護生活を目指していきましょう。
6. 【具体的な対策】ぐるぐる歩きの5つの解消アプローチ
6-1. 軽い役割を与える(例:洗濯物を畳む、ごみ箱チェック)
認知症の方が部屋の中をぐるぐる歩き回る背景には、「何かをしなければならない」という無意識の不安や焦燥感が隠れていることが多くあります。
特に、かつて家庭内で多くの家事を担っていた人ほど、役割を失ったことで「手持ち無沙汰」や「居場所のなさ」を感じやすくなるのです。
このような場合には、軽い日常的な役割を用意してあげることが効果的です。
例えば、洗濯物を一緒に畳んでもらったり、ごみ箱の中を確認してもらったりといった、失敗しても問題にならない簡単な作業がおすすめです。
「これお願いできる?」と声をかけることで、本人の自尊心も守られ、「うろうろしないと落ち着かない」という行動が緩和されるケースもあります。
“行動の目的”を与えることが大切です。
6-2. 散歩・体操など身体活動の時間を日課にする
日中に十分な身体活動が取れていないと、エネルギーを持て余して室内を歩き回るという行動につながりやすくなります。
特に夕方以降の「夕暮れ症候群」が見られる場合は、午前中から昼過ぎにかけて軽い運動を取り入れることで、ぐるぐる歩きの頻度を減らせることがあります。
近所を一緒に散歩したり、ラジオ体操や椅子に座ったままできる体操を習慣づけるのもおすすめです。
大切なのは「日課としてのリズム」を作ること。
リズムが整うことで、不安感も軽減され、室内での目的のない徘徊行動が減少していくことが期待されます。
6-3. 「一緒に探す」など共同行動にする
「何かを探している」ように部屋の中を行ったり来たりしていると感じたことはありませんか?
このような行動には「何か忘れたものを探している」「用事を思い出せない」といった、認知機能の混乱が関係している場合があります。
その際は、「何か探し物かな? 一緒に見つけようか」と共同行動に切り替えることで、本人の不安を和らげると同時に、ぐるぐる歩きの行動が自然と収束していきます。
ここで注意すべきなのは、決して「もう探さなくていい」「何もないでしょ」と否定しないこと。
本人の中では“確かな理由”があるのです。
共感しながら寄り添い、対話を重ねることで、心も行動も落ち着いてくることがあります。
6-4. デイサービスや通所リハビリの活用
四六時中、同じ空間で顔を突き合わせていると、お互いにストレスが溜まりやすくなります。
特に室内でのぐるぐる歩きにイライラが募るようであれば、デイサービスや通所リハビリの利用を前向きに検討してみましょう。
専門スタッフの見守りのもとで、身体活動やレクリエーション、他者との交流ができる場は、本人にとっても生活にハリが出る大切な時間になります。
さらに介護者にとっても、「歩き回る姿が目に入らない時間」が確保されることで、精神的なリフレッシュにもつながります。
一見すると「冷たい」と思えるかもしれませんが、長い介護生活を乗り切るためには「見えない時間」を意図的に作ることも重要なのです。
6-5. 適切な医療・服薬の見直し(かかりつけ医と連携)
ぐるぐる歩きの背景には、身体の不調や服薬の副作用が潜んでいる場合もあります。
例えば、便秘や尿意の不快感、持病の疼痛など、言葉でうまく訴えられないことから落ち着きなく動いてしまうというケースもあります。
また、認知症の進行によって今までとは異なる行動が目立ってきた場合は、医師による適切な評価が必要です。
最近では、認知症の周辺症状(BPSD)に配慮した薬物療法や、身体機能の変化に合わせた薬の調整も行われています。
「気になる変化があれば、かかりつけ医に相談する」という習慣を持つことで、早めに対応できるようになります。
医療との連携は、安心して介護を続けるための心強いパートナーでもあります。
7. 【環境づくり】歩きたくなるのは自然、ならば“安心して歩ける”空間に
認知症の方が部屋の中を何度も行き来したり、目的もなく歩き回るように見える行動は、実はとても自然なことです。
体が元気であれば、何かを探していたり、かつての日常行動を思い出して繰り返そうとしている場合もあります。
「座っていて」と言っても落ち着かないのは、「やるべきことがある」という感覚が強く残っているからです。
そんなときこそ、「なぜ歩くのか」ではなく、「安心して歩ける環境になっているか」を見直してみることが大切です。
7-1. バリアフリー+動線に配慮した室内配置
室内を安全に歩けるようにするには、まず段差の解消や滑りやすい床材の見直しが必要です。
特に、玄関からリビング、トイレ、洗面所、寝室といった主要な場所への動線は、つまずきや転倒のリスクが集中しやすいため、床に敷いてあるマットや電源コードを片づけることが大切です。
たとえば、以前家事をしていた方なら、キッチンや洗濯スペース周辺を無意識に歩き回る傾向があります。
そのため、家具の角を保護したり、夜間の移動に備えて人感センサー付きの足元灯を設置するなど、生活動線に合わせて配慮するとより安全です。
歩行補助のために、手すりの設置や壁に軽く触れながら歩けるような配置も有効です。
7-2. 探し物をしやすくする視覚的サポート(写真ラベルなど)
部屋をぐるぐる歩く行動の理由の1つに、「何かを探しているけど、思い出せない」という状態があります。
このようなときは、家具や引き出し、収納扉に中身の写真やイラストを貼ることで、本人が目的のものを見つけやすくなります。
たとえば、タンスに「くつした」「パジャマ」などの写真と文字ラベルを貼っておくと、何度も開け閉めするストレスを軽減できます。
また、冷蔵庫や薬箱など、重要なアイテムがある場所には「〇〇さんのおくすり」「お茶があるよ」など声掛け風のラベルを添えることで安心感を生み出します。
これらの工夫は、探し物に伴う不安や混乱を防ぎ、無目的に見える徘徊行動を減らす効果が期待できます。
7-3. 閉じこもり防止のために、室内と外部空間の導線も考慮する
「部屋の中をぐるぐる歩く」行動には、外に出たい、気分転換したいという気持ちが隠れていることもあります。
可能であれば、室内からベランダや庭などの外部空間へ自然に導線がつながるように工夫してみましょう。
たとえば、カーテンを開けて日差しを入れる、ベランダに鉢植えや椅子を置くなど、小さな外との接点が「閉じ込められている感覚」を和らげます。
さらに、外出が難しい場合でも、室内に季節の写真や風景カレンダー、昔の旅行写真などを飾ると、気持ちの切り替えにつながります。
デイサービスや地域のサロン利用も含めて、「外とのつながりがある暮らし」を意識することが、過剰な歩行への対処として有効です。
7-4. まとめ
部屋の中をぐるぐる歩く行動は、認知症の進行にともなう自然な行動である一方、周囲が「どう対応してよいか分からない」と感じやすい現象です。
無理に止めようとするのではなく、「安全に、安心して歩ける環境を整える」ことが、本人の心身の安定にも、介護する側のストレス軽減にもつながります。
動線の整理や視覚的な支援、室内外のつながりなど、家庭内でできる工夫は数多くあります。
「なぜ歩くのか」とイライラする前に、「歩いても大丈夫な環境かな?」と目線を変えることが、認知症ケアの第一歩となります。
8. 【ケーススタディ】現場で実際にうまくいった工夫例
認知症の方が家の中を落ち着きなく歩き回るのは、「意味のない行動」ではなく、必ず何らかの理由があるとされています。「探し物をしているつもり」「何かの役に立ちたいと思っている」など、頭や体が求めるままに動いているのです。ここでは、実際の介護現場で実践され、効果のあった工夫を3つご紹介します。それぞれのケースで共通するのは、本人の「気持ち」や「役割意識」に寄り添っている点です。
8-1. キッチンで“お母さんの居場所”を作ったケース
80代の女性が日中ずっとリビングや廊下を行き来し、家族も気が休まらないという相談がありました。特に食事の準備時になると、調理中のキッチンにまで入り込んできて、包丁や火を使う場面での危険が心配されていました。
そこで、思い切ってキッチン内に専用スペースを設け、「お母さんの居場所」として整えました。具体的には、小さめのテーブルに色鉛筆と塗り絵、乾いた野菜をむいてもらう作業などを用意し、本人が「台所仕事に関わっている」と思える環境にしたのです。
この工夫によって、お母さんはキッチンの外をうろうろすることが減り、同時に「何かの役に立っている」という満足感も得られました。また、火元に近づくこともなくなったため、安全面も大きく改善されました。
8-2. 曜日ごとの「おつかいメモ」で不安を解消した事例
一人暮らしの認知症の男性が、毎朝決まった時間に部屋を何度も行ったり来たりして落ち着かないというケースがありました。声をかけると「何か買いに行かなくちゃ」と言うものの、何を買うかは覚えていない。そのため、「どこに行くつもり?」「何を探しているの?」と家族が問いかけるたびに、本人は戸惑い、不安そうな様子になっていました。
このケースでは、週ごとに「おつかいメモ」を曜日別に作成し、冷蔵庫の扉に貼り出すことにしました。月曜は牛乳、火曜はパン、水曜は新聞…というように、本人が「今日は○○を買いに行く」と明確な目的を持てるよう工夫したのです。
結果的に、本人は部屋の中を歩き回る回数が減り、「今日やるべきこと」がわかることで不安感が和らぎました。買い物そのものは家族が代行しましたが、毎朝「おつかい準備をする」ことで、役割を持っているという実感にもつながりました。
8-3. 「探してるフリ」で共感しながら歩いた工夫
70代の女性が、一日中「カバンがない」「財布がない」と言いながら、部屋を歩き続ける様子に家族が疲弊していた例もあります。声をかけても耳を貸さず、夜中でもタンスや押し入れを開け閉めするため、家族は睡眠不足とストレスで限界に近づいていました。
そこで、介護者が考えたのは、「探してるフリを一緒にする」こと。「いっしょに探そうか?」と声をかけ、同じように引き出しを開けたり、部屋の中を一緒に歩きながら探し物ごっこをするスタイルです。
重要なのは、見つけることではなく「共に探している時間を作ること」。すると、女性は安心したような表情を見せ、一定時間が過ぎると「やっぱり見つからないね。まあいいか」と自ら諦めることが増えました。
介護者も「無理に止めさせようとしない」ことで気持ちが軽くなり、結果として両者のストレスが大きく減少しました。このように、意味のある「付き添い歩き」によって、単なる徘徊が共感の時間へと変わる場合もあるのです。
8-4. まとめ
これらの工夫に共通しているのは、「本人の視点に立つこと」と「意味のある役割や行動を作ってあげること」です。認知症によって混乱しやすい状況でも、「何かをしているつもり」や「人の役に立っている実感」があれば、落ち着く場面が増えます。
また、介護者自身が「止めさせよう」とするのではなく、「どう寄り添えるか」を考えることで、日々のストレスも軽減されていきます。一見シンプルな工夫が、介護の質と家族の安心を大きく左右するのです。
9. 【介護者の心を守る】自分の余裕がケアの質を左右する
認知症の方が家の中を何度も行ったり来たりしている姿を見ると、不安になりますよね。「なにか目的があるの?」「落ち着かないのはなぜ?」と、頭では理解しようとしても、毎日のこととなると心がすり減っていくのを感じる方も多いのではないでしょうか。ときには、イライラしてしまう自分に嫌気が差して、自己嫌悪に陥ることもあるかもしれません。
でも、忘れてはいけないことがあります。介護する側の心にゆとりがなければ、良いケアは続けられません。認知症の方が「ぐるぐる歩き回る」行動には意味があることも多いですが、それを四六時中見守ることは、介護者にとって大きな負担です。自分自身のメンタルを守ることは、決してワガママではなく、介護を長く続けるために必要な工夫なのです。
9-1. 見ない選択肢もある:自分が距離を取ることの価値
認知症の人が家の中をうろうろしているのを見るたびに、心がざわついてしまう。それは「意味のない行動に見えてしまう」ことが原因かもしれません。
でも、本人にとっては「なにかしなきゃ」「忘れた用事を思い出したい」という思いや、身体を動かしたい欲求からくる自然な行動なのです。しかし、それを毎日見ている介護者のストレスは計り知れません。特に、家事の合間に見守り続けるのは、心も身体も消耗しますよね。
そんなときは、思い切って「見ない」という選択肢を持ってみてください。たとえば、短時間でも自分が外に出て、誰かに見守りを任せる。あるいは、デイサービスなどを利用して本人に外出してもらう。物理的に距離を取ることで、あなたの気持ちに余白が生まれます。それが、心のクッションになるのです。
9-2. 「ひとりになれる時間」を意識的に確保する
どんなに愛する家族でも、四六時中一緒にいることは精神的な負担になります。介護が長期化する中で、もっとも大切なのは「ひとりになれる時間を持つこと」です。
静かな部屋で、ただお茶を飲むだけの時間でもいいんです。テレビを消して、スマホも置いて、何も考えずに座る。ほんの15分でも、自分だけの静けさに包まれる時間があると、心がずいぶん楽になります。
介護者が疲れてしまうと、認知症の方にも不安や苛立ちが伝わります。だからこそ、「私は休むことが必要なんだ」と自分に言い聞かせて、休む時間を確保することが重要なのです。
そのために、ショートステイの利用も一つの方法です。「自分のために誰かを預けるなんて…」と罪悪感を感じる人もいるかもしれませんが、それは間違いです。あなたが笑顔でいることが、何よりの介護になります。
9-3. 感情のリセット法(例:短時間の散歩、短期入所の利用)
人間だもの、どうしてもイライラする日はあります。そんなときに役立つのが、感情をリセットするための「小さな逃げ道」です。
たとえば、近所を10分歩くだけでも効果があります。深呼吸しながら歩いてみましょう。気持ちが切り替わって、「もう少し頑張れるかな」と思えることもあります。
また、どうしても余裕がないと感じたときは、短期入所(ショートステイ)を活用するのも賢い選択肢です。数日間だけ預かってもらうことで、心と体のエネルギーを補充できます。その間に美容室に行く、映画を見る、外食するなど、普段できないことを楽しんでください。
罪悪感を持たず、自分のケアも介護の一部と考えましょう。そして、回復した気持ちでまた向き合えば、本人にも優しくなれるはずです。
9-4. まとめ
介護において大切なのは、「頑張りすぎないこと」です。「私がしっかりしなきゃ」と思うあまり、自分の限界を見失っていませんか?
認知症の人の「ぐるぐる歩き回る」行動には、意味があります。けれど、それを24時間見守る必要はありません。距離を取ること、休むこと、自分の時間を持つこと。これらはすべて、介護を続けていくために欠かせない、大切な手段です。
誰よりも、あなたの心が元気であること。それが、介護される人にとっても何よりの支えになるのです。
10. 【さらに深く学ぶ】症状を“理解する力”が、家族を救う
「うろうろしないで」「じっとしてて」と声をかけても、また気づけば部屋の中を歩き回っている──。認知症の方と一緒に暮らしていると、こうした場面に心が疲れてしまうことがあります。でも、その行動には、必ず“理由”があるのです。理解しようとする姿勢が、介護する家族の心を軽くしてくれます。ここでは、認知症のタイプごとに異なる歩行行動の特徴や、専門機関・学びの場、さらに書籍や動画などの支援資源について詳しくご紹介します。
10-1. 認知症の種類ごとに異なる「徘徊・歩行」の特徴
「部屋の中をぐるぐる歩き回る」という行動は、どの認知症にも共通するように見えて、実はその背景や目的はタイプによって異なります。
たとえば、アルツハイマー型認知症の場合は、「目的があって動いていたけれど、途中で何をするつもりだったかを忘れてしまう」というケースが多く見られます。「洗濯しようとしたけど途中で忘れた」「冷蔵庫に何か取りに行ったのに思い出せない」といったことが、何度も繰り返されるのです。本人には本人なりの目的があるので、それが達成できないことへの不安が、「うろうろする」という形になって表れます。
一方で、レビー小体型認知症では、幻視や錯覚による混乱から、誰かに追われていると感じたり、知らない場所にいると錯覚して歩き回ることがあります。また、前頭側頭型認知症では、同じ行動を繰り返す常同行動が特徴で、「理由はわからないけど同じルートを行ったり来たりする」ことも少なくありません。
つまり、「なんで歩き回るの?」ではなく、「どのような認知症の可能性があるのか」「この行動は何を意味しているのか」を探る視点が大切になります。行動の“理由”を理解できれば、「止めさせる」のではなく「安心して過ごせる環境を整える」ことができるようになります。
10-2. 相談機関・学びの場(地域包括支援センター、講座)
いくらインターネットで調べても、実際の介護はケースバイケース。だからこそ、地域にある相談機関を活用することが、家族にとっての心の支えになります。特に身近な相談先として知られるのが「地域包括支援センター」です。全国どの地域にも設置されており、認知症に関する相談や情報提供、ケアマネジャーとのつながり支援まで、総合的にサポートしてくれます。
また、各自治体や介護支援団体が開催している「認知症サポーター養成講座」や、民間団体による「家族介護者向け学習会」も有効です。講座では、脳の働きや症状の種類だけでなく、「どのように接するか」「どこまで見守ればいいのか」といった、実生活で役立つ知識を学べます。
参加者同士で交流できることもあり、「うちだけじゃなかったんだ」と共感し合えることも、精神的な大きな支えになります。
10-3. 書籍・動画・専門家による支援の活用
毎日の介護の中で、自分だけでは解決できない悩みもたくさん出てきますよね。そんな時に力になるのが、書籍や動画、そして専門家の存在です。
たとえば、YouTubeでは「認知症ケア専門士」などが発信している動画が多数あり、5~10分程度で視覚的に学べるコンテンツが人気です。「どう声をかければ安心してもらえるのか」「なぜ同じことを繰り返すのか」など、現場の経験に基づいたリアルなアドバイスが得られます。
また、書籍としては、医学的な内容だけでなく、家族目線の体験記やケアの工夫が紹介されている実用書も多く出版されています。「こうしてみたらうまくいった」「これは逆効果だった」といった、他の家族の事例が参考になります。
そして、なにより心強いのが、個別相談ができる専門家の存在です。費用はかかりますが、オンラインでも50分5,000円ほどで受けられるものもあり、第三者の専門的な視点で状況を整理してもらえることは非常に有効です。
10-4. まとめ
認知症の方が「部屋の中をぐるぐる歩き回る」ことには、必ず“背景”や“意味”があります。それを理解する努力が、介護する家族の心を守り、よりよい関係を築く第一歩になるのです。
そのためには、認知症の種類による違いを知ること、専門機関に頼ること、そして書籍・動画・相談窓口を使って学び続けることがとても大切です。
「わからないこと」を放っておかず、「知ろうとすること」が、家族みんなの笑顔を守る力になります。
11. おわりに:「ぐるぐる歩く」その姿の奥にある“想い”に寄り添って
11-1. 認知症になっても「役割」と「居場所」は必要
認知症の方が部屋の中を何度もぐるぐる歩き回る姿には、単なる「落ち着きのなさ」では済まされない深い理由が隠されています。
例えば、かつて家事や育児に忙しく立ち働いていた高齢の母親が、現在では日常の中で何も「すること」がない状態になると、かつての“役割”を無意識に探して歩き回ることがあります。
これまで「家族のために役に立ってきた」という実感が、「今の自分」には感じられないことが、不安や混乱となって表れているのです。
認知症であっても、人は誰かの役に立ちたいという気持ちを持ち続けています。
「洗濯物をたたんでほしい」「一緒に野菜を切ってほしい」など、できる範囲で役割を持ってもらうことが、その人にとっての“居場所”につながります。
たとえ上手にできなくても、「ありがとう」「助かったよ」と声をかけることで、「ここにいていいんだ」という安心感が生まれます。
また、無目的に見える行動の背景には、“何かをしなければ”という焦りや混乱があることも多いです。
このようなときには、家庭内に小さな“仕事”や“決まった習慣”を用意しておくと、落ち着きや安心感につながる可能性があります。
うろうろ歩くのは、もしかすると、失った役割を自分の中で探しているサインなのかもしれません。
11-2. 家族の“頑張りすぎない勇気”が介護を続ける鍵
認知症の介護は、体だけでなく心にも大きな負担がかかります。
特に「ぐるぐる歩く」行動を四六時中見ていると、介護する側の心が休まる時間がありません。
「なぜ歩き回っているの?」「どうして落ち着いてくれないの?」と理解できないと、知らず知らずのうちにイライラが募ってしまうものです。
そんなときに大切なのは、「一人で背負いすぎない」こと。
たとえば、デイサービスなどの介護サービスを利用して一時的に離れる時間を作ることも、自分を守る立派な選択です。
「そんなことしてもいいのかな」「冷たいと思われないかな」と罪悪感を抱く必要はありません。
むしろ、介護者が心にゆとりを持つことは、長く向き合っていくために不可欠です。
外からは「ただ歩き回っているだけ」に見える行動にも、実はその人なりの理由や想いがあります。
それを完全に理解することは難しくても、「もしかしたら、こんな気持ちなのかも」と想像することだけでも、関わり方は大きく変わります。
そして、頑張りすぎない自分を認めてあげることが、介護生活を続ける上で何よりも重要なことなのです。