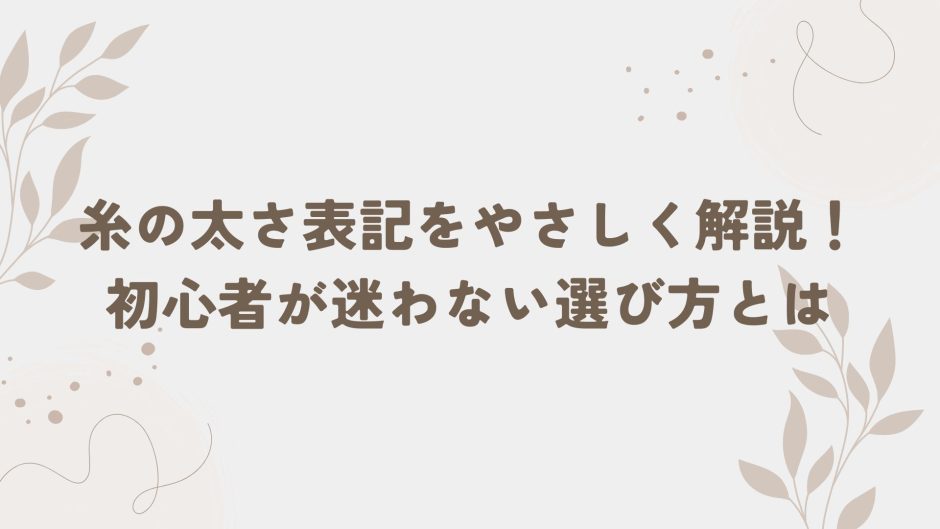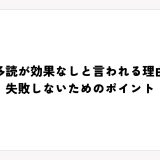服や生地のタグに書かれている「20/-」や「40/2」といった謎の数字。見たことはあるけれど、意味まではよく分からない……そんな方も多いのではないでしょうか。この記事では、糸の太さを示す「番手」や「デニール」「デシテックス」などの表記について、基礎から丁寧に解説していきます。
1. 糸の太さ表記って何?最初に知っておきたい基礎知識
洋服や布製品の素材を理解する上で欠かせないのが、「糸の太さ」の知識です。実は糸の太さには明確な表記ルールがあり、それを知らないと生地の厚さや風合い、丈夫さなどを正しく判断できません。「20番手」「30/2天竺」「40デニール」といった表記を見かけたことがあるかもしれませんが、これはすべて糸の太さや構造を示す情報です。ここではまず、なぜ糸の太さが重要なのか、なぜ複数の表記方法があるのか、そして具体的な表記の種類についてわかりやすく解説します。
1.1 糸の太さはなぜ重要?生地・製品に与える影響とは
糸の太さは、生地の見た目や触り心地だけでなく、製品の耐久性や用途にも直結する重要な要素です。たとえば、分厚くて丈夫なデニム生地には10番手ほどの太い糸が使われます。一方、繊細で軽やかなワイシャツには80番手〜100番手のような極細の糸が使われます。糸が細くなるほど、生地は薄くしなやかになり、肌触りもなめらかになりますが、その分強度は落ちやすくなります。
また、糸の構造にも注目が必要です。たとえば「30/2天竺」という表記では、30番手の糸を2本撚り合わせた「双糸(そうし)」を使用しています。同じ30番手の糸でも、「30/-天竺(単糸)」と比べると、双糸は強度が高く、しっかりした生地感になります。つまり、番手 × 糸構造の組み合わせで、生地の最終的な特徴が決まるのです。
1.2 表記が複数ある理由:天然繊維と化学繊維の違い
「糸の太さ」と一口に言っても、実は使われる素材によって表記方法が異なります。これは、天然繊維と化学繊維で測り方の基準が違うからです。
たとえば、綿やウールなどの天然繊維では「番手(バンテ)」という表記を使います。これは、一定の重さ(1ポンド)に対して、何ヤードの長さがあるかで太さを表します。つまり、数字が大きいほど細いという逆転のルールが特徴です。例:1番手(太い) → 30番手(細い) → 100番手(極細)
一方、ナイロンやポリエステルなどの化学繊維では、「デニール(denier)」や「デシテックス(dtex)」という単位が使われます。これらは長さあたりの重さで糸の太さを示すもので、数字が大きいほど太いという自然な感覚です。例:40デニールのタイツは薄手、80デニールは厚手
このように、繊維の種類によって測定基準が異なるため、表記方法も複数存在するのです。それぞれの特徴を知ることで、製品選びや素材選定がより的確にできるようになります。
1.3 表記の種類一覧:番手・デニール・デシテックス 他
ここでは、糸の太さを表す代表的な表記方法を一覧で紹介します。それぞれの特徴を理解しておくと、生地の厚さや風合いを見極めやすくなります。
- 番手(Cotton Count:英式番手)
主に綿やウールなど天然繊維に使用。
一定の重さに対して糸の長さが長いほど、細いとされます。
例:10番手(太め)、30番手(中くらい)、100番手(極細)
数字が大きいほど糸が細いのが特徴。 - デニール(denier)
主にナイロン・ポリエステルなどの化学繊維に使用。
長さ9000メートルあたりの質量(g)で太さを測ります。
例:40デニール(薄手タイツ)、80デニール(厚手タイツ)
数字が大きいほど糸が太い。 - デシテックス(dtex)
デニールと同様に化学繊維で使われますが、より国際的な単位。
10000メートルあたりの質量(g)で計算します。
EU圏では主にこちらが使われています。 - 生地表記(例:30/-天竺、20/2フライスなど)
糸の番手と構造を合わせて示す表記方法。
例:「30/-天竺」は30番手の単糸で編まれたニット、「20/2」は20番手の双糸(2本撚り)。
同じ番手でも、単糸(/-)と双糸(/2)では生地の厚みや強度が異なります。
1.4 まとめ
糸の太さ表記は、生地選びや製品開発に欠かせない基本知識です。特にアパレル業界では、「20/2」「40/1」「100番手」などの表記が日常的に使われており、正しく理解していないと素材の意図を読み取ることができません。
天然繊維には「番手」、化学繊維には「デニール」「デシテックス」といった表記があり、測り方が根本から異なります。そのため、同じ「40」という数字でも、表記方法が違えば意味も大きく変わるのです。
また、「30/2」「40/-」のように、糸の本数や撚り方も併せて記載されることで、生地の厚み・丈夫さ・風合いに違いが生まれます。数字の意味と構造を合わせて理解することで、より的確な製品選びができるようになります。
2. 「番手」とは?衣料用テキスタイルで最も使われる単位
衣料用のテキスタイル(繊維製品)を選ぶときに、避けて通れないのが糸の「番手(ばんて)」という単位です。これは、布の厚みや手触り、通気性などを左右する糸の太さを表すための基準であり、特に綿素材の生地では最も多く使われています。数字が並ぶ「30/-天竺」や「40/2天竺」といった表記の中にも含まれており、これらの読み解き方が分かれば、生地の特性をある程度イメージすることができます。
たとえば、Tシャツやワイシャツを買うとき、生地の厚みや肌ざわりで迷った経験がある方も多いはずです。そんなとき、この番手の知識があると、目的に合った生地を的確に選べるようになります。ここからは、番手の定義から、計算の仕組み、具体的な使用例や読み方まで、しっかり解説していきましょう。
2.1 番手の定義と計算式:綿番手(Ne)の考え方
番手とは、主に綿糸の太さを示す単位であり、正式には「綿番手(コットン番手)」または「Ne(Number English)」と呼ばれています。番手の数値が示すのは「1ポンド(約453.6g)の綿糸を何ヤード(約91.44m×○)の長さにしたか」で決まります。つまり、数字が大きくなるほど、同じ重さでたくさんの長さがとれる → 糸が細いということになります。
計算式で表すと:
番手(Ne)= 糸の長さ(ヤード) ÷ 糸の重さ(ポンド)
このように、番手は「長さ ÷ 重さ」で決まり、単位が大きくなると細い糸、小さくなると太い糸を意味します。
たとえば、「1番手」は、1ポンドでわずか840ヤードしかない、とても太い糸です。一方で「100番手」は、同じ1ポンドで8万4千ヤードもある、非常に細い糸なのです。
2.2 数字が小さい=太い、数字が大きい=細い理由
「番手は数字が小さいほど太く、数字が大きいほど細い」というルールに最初は戸惑うかもしれません。しかし、前述の通り一定の重さでどれだけ長く糸がとれるかを示しているため、このルールが成立します。
たとえば、10番手の糸と100番手の糸を比べると、10番手の方が短い長さしかとれない=太い、というわけです。現実の製品で見ると、ジーンズやデニム素材などは太い10番手が使われることが多く、薄手のワイシャツや高級ドレスシャツには細い80〜100番手が使用されます。
この違いを感覚で理解するには、実際に手に取って触れるのが一番ですが、番手の数字だけでもある程度の生地感を予測できるようになります。
2.3 実使用例で比較:10番手 vs 40番手 vs 100番手
ここで、具体的な例を見てみましょう。
- 10番手:非常に太くて丈夫な糸。主にデニムや厚手のワークシャツに使われます。生地にハリとコシがあり、長年使える耐久性があります。
- 40番手:Tシャツに多く使われる一般的な番手。やや薄手で、柔らかい肌ざわりが特徴です。吸湿性や着心地に優れており、インナーや夏用衣料に適しています。
- 100番手:極細の高級糸。ワイシャツやブラウス、高級下着などに使用され、シルクのように滑らかな風合いを持ちます。ただし強度は弱めなので慎重な取り扱いが求められます。
このように、同じ「綿」でも番手によって用途が大きく異なります。
2.4 単糸(/-)と双糸(/2)の違い:見た目・厚さ・強度
番手表記にはスラッシュ( / )の後ろに数字がついていることがあります。 たとえば「30/-」や「30/2」などのように書かれている場合です。 これは、単糸か双糸かを表しています。
- 単糸(たんし):「/-」や「/1」と表記
1本の糸だけで編まれたもの。軽くて通気性に優れていますが、摩擦や引っ張りにやや弱いという特徴があります。 - 双糸(そうし):「/2」と表記
2本の単糸を撚り合わせた糸。見た目がしっかりしていて、強度も高く、長持ちする生地になります。肌触りもしなやかで、高級感があります。
同じ番手でも、単糸と双糸では仕上がりの厚さや質感が大きく異なります。 単糸の生地は軽やかでカジュアルに、双糸の生地は密度が高く高級な印象になります。
2.5 実例で理解:30/-天竺と30/2天竺はどう違う?
たとえば、Tシャツによく使われる「天竺(てんじく)編み」の生地で「30/-天竺」と「30/2天竺」があるとしましょう。どちらも糸の太さ自体は30番手で同じですが、使用する糸の構成が異なります。
「30/-天竺」は30番手の単糸で編んだ生地。これに対して「30/2天竺」は30番手の双糸を使用しているため、実質的には60番手相当の太さになり、しっかりとした厚みと強度が出ます。
双糸は単糸に比べて、伸びにくく型崩れしにくいため、洗濯に強く、長持ちしやすいというメリットがあります。一方で、単糸の天竺は通気性に優れており、柔らかい着心地が特徴です。用途や着用シーンに合わせて選ぶことが大切です。
ちなみに、同じ生地厚になるように設計されることもあり、20/-(太い単糸)と40/2(細い双糸)がほぼ同等の厚みになるケースもあります。
3. 素材別に異なる番手の考え方
糸の「太さ」を示す番手(ばんて)は、素材ごとに単位や基準が異なるため、少し複雑に感じられるかもしれません。
たとえば「綿(めん)」と「ウール(毛)」では、同じ「40番手」と書いてあっても、実は太さの意味合いが異なります。
これは、それぞれの素材で糸をどのように測るかという考え方に違いがあるからです。
ここでは代表的な素材で使われる番手の種類と、その違いについて分かりやすく解説していきます。
また、海外との表記の違いについても触れながら、糸選びで迷わないための基礎知識をしっかり押さえていきましょう。
3.1 綿番手(Ne)と毛番手(Nm)の違い
綿(コットン)の番手には「Ne(Number English)」という単位が用いられます。
これは「1ポンド(約453g)の綿で何ヤードの長さの糸が引けるか」を基準にした数値で、数字が大きくなるほど糸は細くなります。
例えば、「20番手」は比較的太めの糸で、Tシャツやデニムに使われることが多く、「100番手」になると非常に繊細なワイシャツ用の糸になります。
一方、ウールなど毛素材に使われるのが「Nm(Number metric)」と呼ばれる「メートル番手」です。
こちらは「1gの糸で何メートルの長さがあるか」という指標で、Neとは逆に「数字が大きいほど細い」という関係は同じですが、計算の仕組みが違います。
つまり、同じ「40番手」と言っても「Ne40」と「Nm40」では長さも太さも違ってくるのです。
この違いを理解しておかないと、「Ne40のコットン糸」と「Nm40のウール糸」を同じ太さと誤解してしまう可能性があります。
番手の単位を確認することは、目的に合った生地選びにおいて非常に大切です。
綿=Ne、毛=Nmという組み合わせをまずはしっかり覚えておきましょう。
3.2 麻番手(Lea)、絹番手(Denier Silk)も知っておくべき?
綿や毛と同様に、麻や絹(シルク)にも独自の番手表記があります。
麻素材では「リネン番手(Lea)」が使われ、「1ポンドの麻糸で300ヤードの長さが何本取れるか」という仕組みで数値化されます。
こちらもやはり「数字が大きいほど細い」ことになります。
リネンシャツや夏用のスーツ地などでよく使用される繊維です。
絹(シルク)の場合は少し特殊で、「デニール(Denier)」という単位が用いられます。
これは「9000メートルの糸の質量が何グラムか」で表される単位で、数字が大きいほど太いという他の番手とは逆の特徴があります。
たとえば「21デニールの絹糸」は細くて繊細ですが、「70デニール」になるとしっかりした厚みが出てきます。
このように、シルクは美しい光沢や滑らかさが魅力の素材なので、デニールでの細やかな調整が製品の質に直結します。
また、ナイロンやポリエステルなどの化学繊維も同様に「デニール」で太さが示されるため、絹と化学繊維の違いを知る上でもこの単位は重要です。
「麻=Lea」「絹=デニール」と押さえておくと、素材ごとの番手の違いが整理しやすくなります。
3.3 海外表記との比較:イギリス式・フランス式・日本式の違い
糸の番手には国ごとの独自表記も存在し、グローバルな取引ではこれらの違いを正確に理解しておく必要があります。
代表的なのが「イギリス式」「フランス式」「日本式」の3つです。
イギリス式(English Cotton Count:Ne)は先ほど述べた綿番手の基準で、主に英語圏で使用されています。
「20s」「40s」といった表記は英式番手を意味し、特にアメリカのコットン製品では一般的です。
一方でフランス式(Tex、dTex)は、重量に基づいた表記方法で、10,000メートルの糸の重さ(g)を元にしたデシテックス(dTex)などが使われます。
これにより正確な太さや密度の表現が可能で、特にヨーロッパでは衣料品やスポーツウェアの分野で重宝されています。
日本式は素材ごとの番手が混在しているため、業界では「Ne」「Nm」「Lea」「Denier」といった海外基準をそのまま用いることが一般的です。
そのため、日本国内であっても「20/1」や「30/2」などの表記を見かけることが多く、これは「単糸・双糸」の区別も含んだ番手表記となります。
たとえば「40/2天竺」という記載なら、「40番手の糸を2本撚った双糸で編んだ生地」という意味になります。
これはイギリス式の番手Neを基準にしているため、「フランス式のTex」や「シルクのデニール」とは別物です。
このように、各国・各素材によって基準が大きく異なるため、単位の種類をしっかり確認することがとても重要です。
3.4 まとめ
糸の太さを示す「番手」は、一見すると単純な数値に見えますが、素材の種類や国の基準によって意味が大きく変わってくることが分かりました。
綿なら「Ne」、毛なら「Nm」、麻は「Lea」、絹は「デニール」、さらに国ごとに「イギリス式」「フランス式」「日本式」といった表記の違いが存在します。
これらを混同してしまうと、目的と異なる太さの糸や生地を選んでしまう可能性があります。
そのため、糸の購入や生地選びの際は、番手の単位に必ず目を向けて、素材や用途に合ったものを選ぶことが重要です。
ファッションや繊維業界に関わる人だけでなく、ハンドメイドや裁縫を楽しむ方にとっても、番手の理解は作品の仕上がりを左右する大切なポイントになります。
4. デニール(D)とデシテックス(dtex)の違いと使い方
糸の太さを表す単位には、いくつかの種類があります。
代表的なものとして番手(cotton count)、デニール(denier:D)、そしてデシテックス(decitex:dtex)があります。
それぞれが異なる繊維や用途に合わせて使われており、特に化学繊維の世界では「デニール」と「デシテックス」が主流です。
このセクションでは、それぞれの単位の違いや特徴、使い分け方を詳しく見ていきましょう。
4.1 化学繊維で使われる太さの単位とは?
化学繊維、たとえばナイロンやポリエステルなどでは、綿や麻で使われる「番手」ではなく、デニール(D)やデシテックス(dtex)という単位が使われます。
これは、天然繊維と化学繊維で糸の構造や製法が異なるため、太さの測定方法も違うからです。
デニール(denier)は、9000メートルあたりの糸の重さ(g)を表します。
つまり、「1D = 9000mあたり1gの重さの糸」という意味です。
一方、デシテックス(dtex)は、10000メートルあたりの糸の重さ(g)です。
「1dtex = 10000mあたり1g」ですので、デニールより少し細かい単位と言えます。
このように、同じ糸でも測る基準が違うため、用途によって単位を使い分ける必要があります。
ヨーロッパではdtex、日本やアメリカではDが一般的に使われています。
化学繊維の表示を見るときには、どちらの単位で書かれているのかを意識することが重要です。
4.2 デニールとデシテックスの関係:1.11の法則
デニール(D)とデシテックス(dtex)は、それぞれ「9000mあたりの重さ」「10000mあたりの重さ」を表しているため、単純に換算ができます。
ここで便利なのが「1.11の法則」です。
具体的には、以下の関係があります。
1デニール ≒ 1.11デシテックス
1デシテックス ≒ 0.9デニール
このように、デニールに1.11を掛けるとおおよそのデシテックスに変換できます。
たとえば「70Dのタイツ」は「77.7dtex(≒70×1.11)」と表すことができます。
計算が非常にシンプルなので、現場ではこの換算ルールがよく使われています。
もちろん、厳密な科学実験などでは正確な値を使う必要がありますが、日常的なファッション用途ではこの「1.11換算」で十分とされています。
4.3 デニール別の製品例:30Dタイツ vs 80Dタイツ
デニールは、私たちが普段身につける衣類、とくにストッキングやタイツ、レギンスなどの厚みの目安としてよく使われています。
例えば、30デニール(30D)のタイツは非常に薄く、透け感がある仕上がりになります。
春や秋など少し肌寒い季節にぴったりで、肌をうっすらとカバーしてくれます。
それに対して、80デニール(80D)のタイツになると、かなり厚手になります。
しっかりと不透明で防寒性も高く、冬場のコーディネートに欠かせない存在です。
このように、デニールの数字が小さいほど糸は細く、数字が大きいほど太くなるという性質があります。
番手とは逆の関係性であることに注意しましょう。
番手の場合は数字が小さいほど糸が太いですが、デニールやデシテックスでは数字が大きいほど太くなります。
この違いを理解しておくと、製品の選び方や表示の読み解きがずっと楽になります。
4.4 番手・デニール・dtexの換算チャートで一括理解
異なる単位が混在していると、どれが太いのか細いのか分かりにくく感じますよね。
そこで便利なのが番手・デニール・デシテックスの換算チャートです。
以下は一般的な目安です(※繊維の種類や撚りの強さによって多少の差があります)。
| 番手(綿糸) | デニール(D) | デシテックス(dtex) | 厚さのイメージ |
|---|---|---|---|
| 10番手 | 約180D | 約200dtex | 厚手・デニムなど |
| 20番手 | 約90D | 約100dtex | やや厚手・Tシャツ |
| 40番手 | 約45D | 約50dtex | やや薄手・カットソー |
| 80番手 | 約23D | 約25dtex | 薄手・ワイシャツ |
このチャートを見ると、番手の数字が大きくなるほど細くなるのに対して、デニールやデシテックスは数字が大きいほど太くなることが分かります。
たとえば、40番手の糸を使ったTシャツと、45Dのタイツはだいたい同じような糸の太さと考えられますが、用途や撚り方によって風合いは大きく異なります。
用途や素材に応じて、適切な単位で選ぶことが大切です。
生地の厚みを正確に把握するには、単位とその意味を正しく理解することが第一歩です。
5. 糸の太さと生地の厚み・風合いの関係性
5.1 糸が太いほど厚い?でも重さや撚りも関係
糸の太さは、一般的に「番手(ばんて)」という単位で表されます。番手の数字が小さいほど糸は太く、大きいほど細くなります。たとえば16番手の糸は太く、40番手や60番手の糸はかなり細い部類に入ります。よくある疑問の一つに「糸が太ければ生地も厚くなるの?」というものがありますが、これは一概には言い切れません。
確かに、単純に考えれば太い糸を使えばそのぶん生地はしっかりと厚くなります。たとえば、一般的なデニムには10番手程度の太い糸が使われるため、ずっしりとした厚みがあります。一方で、ワイシャツのようにさらりとした肌触りが求められる生地には80~100番手の極細糸が使われます。
ただし、それだけでは不十分で、「生地の厚み」には糸の撚り(より)の強さや糸の本数(単糸か双糸か)も関係してきます。撚りの強さによって糸の密度や締まり具合が変わるため、同じ番手でも風合いや厚みが異なります。つまり、番手は糸の「太さの目安」ではありますが、それだけでは生地の厚さは決まりません。
5.2 強撚糸と甘撚糸:肌触りと質感の差を生む要素
糸を作る過程で欠かせない工程の一つが「撚り(より)」です。撚りとは、繊維をねじって糸にすることを指しますが、その撚りの強さによって糸の性質が大きく変化します。
たとえば、撚りが強い「強撚糸(きょうねんし)」を使った生地は、表面がさらりとしており、ひんやり感も感じやすく、夏場の衣類などによく使われる傾向があります。糸が締まっているため、シャリ感があり、ドライタッチな風合いが特徴です。
一方で、「甘撚糸(あまよりし)」は、ゆるく撚られているため、ふんわりとした優しい肌触りになります。これはタオル地やベビー服など、柔らかさが求められる製品にぴったりです。撚りが甘い分、空気を多く含みやすく、保温性も高まる特徴があります。
このように、同じ番手でも撚りの強弱によって生地の風合いや見た目は大きく変わるため、番手だけでは語れない奥深さがあるのです。
5.3 糸の本数と強度:単糸・双糸・三子糸の違い
番手表記でよく見かける「30/-」や「40/2」などの記号。これは糸の構成を示しています。前の数字は番手、後ろの「/1」「/2」などは撚られている糸の本数を示しています。
まず、「単糸(たんし)」は、1本の糸をそのまま使ったもの。表記では「30/-」や「30/1」と書かれます。この単糸で編まれた生地は、軽くて柔らかい反面、摩擦や引っ張りに弱い傾向があります。
次に「双糸(そうし)」は、2本の単糸を撚って1本にしたもの。「30/2」「40/2」などと表されます。双糸は単糸よりも丈夫でしっかりした生地になりやすく、毛羽立ちも抑えられるため高級感が出ます。
さらに「三子糸(みこいと)」になると、3本の糸を撚り合わせたものになり、強度と厚みがさらにアップします。Tシャツやポロシャツなどで厚手でしっかり感のある製品に使われることが多いです。
つまり、同じ番手でも糸の本数が増えることで厚みや強度が変わるため、番手だけでなく構成もセットで確認するのがポイントです。
5.4 Tシャツ・シャツ・デニム生地の厚み比較(番手別)
番手ごとの生地の使われ方を知ると、糸の太さと厚みの関係がよりイメージしやすくなります。以下に、衣類別にどの番手がよく使われているかを比較してみましょう。
Tシャツ:一般的には16~40番手の範囲で選ばれます。16番手はかなり厚手でがっしりした着心地。スポーツ系Tシャツやしっかりした素材のものに使われます。一方、30番手や40番手は薄手で柔らかく、カジュアルでライトな風合いになります。
ワイシャツ・ドレスシャツ:こちらでは80~100番手といった非常に細い糸が使用されます。軽くて滑らかな生地が好まれるため、繊細な双糸で編まれたものが一般的です。
デニム:丈夫さが最優先されるため、通常10番手前後の太い単糸や双糸が使用されます。これによって厚手で耐久性の高い生地が生まれ、履き込むほどに風合いが増していきます。
このように、同じ「生地」と言っても使われている番手の違いで用途や風合いがまったく異なるのです。商品選びの際には「番手の数字」に注目することで、求める着心地や機能性に合ったものを選びやすくなります。
6. 覚えておくと便利な糸太さ早見表&換算表
糸の太さにはさまざまな表記方法がありますが、それぞれの単位が異なるため混乱しやすいですよね。
ここでは、糸の太さを表す「番手(Ne)」「デニール(D)」「デシテックス(dtex)」の違いをしっかり押さえたうえで、生地の厚さ感や用途別の目安がひと目でわかるように整理しました。
また、番手・デニール・デシテックスの相互換算チャートや計算式も紹介していますので、素材選びや生地企画の際にぜひ活用してください。
6.1 番手(Ne)別の生地厚さイメージ一覧表
番手とは、主に綿などの短繊維に使用される糸の太さの単位で、「1番手」「10番手」「30番手」「100番手」などのように数字で表記されます。
この数字が小さいほど糸は太くなり、大きくなるほど糸は細くなるという特徴があります。
以下に、番手ごとの一般的な用途と生地の厚みのイメージをまとめました。
| 番手(Ne) | 生地の厚み | 主な用途・例 |
|---|---|---|
| 10番手 | 厚手 | デニム、厚手Tシャツ、トレーナー |
| 16番手 | やや厚手 | 一般的なTシャツ、トレーナー |
| 20番手 | 中厚 | カジュアルシャツ、肌着 |
| 30番手 | やや薄手 | カットソー、夏用Tシャツ |
| 40番手 | 薄手 | シャツ地、ブラウス |
| 80〜100番手 | 超極細 | 高級ワイシャツ、ハンカチ |
たとえば、デニムによく使われるのは10番手。これはとても太い糸で、ざっくりとした風合いのある生地になります。
一方で、ワイシャツには80〜100番手といった細い糸が使われ、しなやかで上品な仕上がりとなります。
6.2 デニール(D)/デシテックス(dtex)の用途別早見表
「デニール(denier)」や「デシテックス(dtex)」は、主に化学繊維(ポリエステル、ナイロンなど)に使われる糸の太さの単位です。
どちらも糸の重さを基にした単位で、数値が大きいほど糸が太くなります。
デニールは「9000メートルあたりの質量(g)」、デシテックスは「10000メートルあたりの質量(g)」で測定されます。
| デニール(D) | dtex(参考値) | 用途例 |
|---|---|---|
| 10D | 11dtex | ストッキング、超極薄のレース素材 |
| 30D | 33dtex | 薄手タイツ、インナー向け生地 |
| 70D | 77dtex | 標準的なタイツ、軽量ナイロン |
| 210D | 233dtex | リュックやテント素材 |
| 420D | 466dtex | 登山用バッグ、強度重視のアウトドア素材 |
たとえば、30デニールの糸はタイツやストッキングなど、肌に密着する繊細な生地によく使われます。
一方で、420デニールになるとバックパックやアウトドア用のタフな生地として採用されるほど丈夫です。
6.3 番手⇔デニール⇔dtex:換算チャート&計算式
ここでは、糸の太さを表す3つの単位を相互に換算できるよう、簡易チャートと基本的な計算式を紹介します。
6.3.1 換算チャート
| 番手(Ne) | デニール(D) | dtex |
|---|---|---|
| 10 | 200〜220 | 222〜244 |
| 20 | 100〜110 | 111〜122 |
| 30 | 66〜73 | 74〜81 |
| 40 | 50〜55 | 56〜61 |
| 100 | 20前後 | 22前後 |
この表はあくまで目安です。糸の素材や撚り方によって多少の差が出るため、実際にはサンプルや仕様書で確認することが大切です。
6.3.2 計算式
番手、デニール、dtexをそれぞれ換算する際の基本的な式はこちらです。
- 番手(Ne)からデニール(D)への換算
D ≒ 5315 ÷ Ne(※綿糸換算) - デニール(D)からdtexへの換算
dtex = D × 1.11 - dtexからデニール(D)への換算
D = dtex ÷ 1.11
たとえば、30番手の綿糸をデニールに換算すると、
5315 ÷ 30 = 約177デニールとなります。
このように単位を使い分けたり換算したりすることで、用途や生地の方向性に合わせた適切な素材選びが可能になります。
生地の厚みや耐久性をコントロールするために、これらの知識は欠かせません。
7. 実務に役立つ!番手表記の読み解き事例集
番手表記は、生地や糸に関する専門用語の中でも、もっとも実務で登場する頻度が高い表記です。
特にアパレル業界や生地販売、服飾制作に携わる方にとって、番手表記を正しく読み取ることは、生地選びや提案の正確性を大きく左右します。
ここでは、代表的な番手表記の読み方と、実際の商品タグや通販での注意点をわかりやすく解説します。
具体的な読み解き方の事例を通して、実務に活かせるスキルとして番手の知識を身につけていきましょう。
7.1 よくある表記パターンを読み解く:20/-天竺・40/2フライスなど
番手表記でよく目にするのが、「20/-天竺」「30/2天竺」「40/2フライス」といった形です。
これらの数字には、糸の太さだけでなく、糸の構成(単糸か双糸か)も示されています。
たとえば、「20/-天竺」の場合、「20」は番手(太さ)、「-」は単糸であることを意味します。
単糸とは、1本の糸だけで構成された糸のことで、柔らかさや軽さを出したいときによく使われます。
一方、「40/2フライス」となると、「40」は細めの番手で、「/2」は2本の糸を撚り合わせた双糸を表しています。
双糸は単糸よりも強度が高く、型崩れしにくいのが特長です。
ここで注目したいのが、同じ厚みに見えても糸の構成によって性質が異なるという点です。
たとえば、「20/-(単糸)」と「40/2(双糸)」は、結果的に同じ程度の生地の厚さになりますが、風合いや強度に違いが出てきます。
また、「30/-天竺」や「16/2裏毛」などもよく使われる組み合わせで、それぞれ用途に応じて選ばれる糸の種類や構成があることを知っておくと、より適切な生地選定が可能になります。
7.2 商品タグの「番手表記」から読み取れること
店舗や展示会、工場の現場などで目にする「商品タグ」には、番手に関する重要な情報が記載されていることがあります。
特にTシャツやシャツなどの製品では、「30/1天竺」「16/2裏毛」などの表記が使われており、それによって生地の厚み・柔らかさ・耐久性を把握できます。
たとえば、「30/1天竺」とあれば、「30番手の糸を1本で編んだ生地」、つまり比較的薄手で柔らかいTシャツ素材であることがわかります。
これに対して「16/2裏毛」であれば、16番手という太めの糸を2本撚り合わせた、しっかり厚手の裏毛素材ということになります。
商品タグの番手表記を読み解けると、カタログやPOPに書かれている文言だけでなく、実際の着心地やシルエットにも目が届くようになります。
これは、店頭での提案力やオンライン販売での説得力にもつながる重要な知識といえるでしょう。
7.3 ネット通販で生地を選ぶときの注意点と読み方
ネット通販で生地を購入する際、実際に手に取ることができないため、番手表記を頼りに判断する力が非常に重要になります。
特に「20/-」「30/1」「40/2」などの表記があるときには、その意味を正しく読み取って、求めている生地の厚さや風合いと合っているかどうかを確認しましょう。
まず押さえておきたいのは、数字が小さいほど糸は太く、生地は厚くなるという基本法則です。
つまり「16番手」はかなり太めの糸で、「100番手」になると非常に細い糸ということになります。
次に見るべきポイントが、スラッシュ( / )の後ろの数字です。
「/1」や「-」とあれば単糸、「/2」は双糸を意味し、双糸はしっかりめ、単糸は軽やかな印象の生地になります。
たとえば、「30/2天竺」とあれば、「細めの糸を撚って強度を持たせたTシャツ向けの生地」と予測できます。
反対に「20/-天竺」は、「太めの糸で柔らかくざっくりした質感」だと判断できます。
さらに、生地名が「フライス」「裏毛」「天竺」などで異なるため、番手だけでなく組み合わせの生地種にも注意が必要です。
読み方を覚えると、「この表記なら夏向けだな」「これは冬物に良さそう」など、通販でも的確に判断できるようになります。
7.4 まとめ
番手表記は、糸の太さと構成の情報を一目で把握できる非常に便利な指標です。
「30/-」や「40/2」などの表記を読み解けるようになると、生地の選定や製品の特性判断が格段にスムーズになります。
店舗での商品提案はもちろん、ネット通販でも「厚さ」「強度」「柔らかさ」などを番手から見抜く力が重要です。
実務においては、特に番手×構成×生地種の組み合わせを理解しておくことで、より的確な判断と提案が可能になります。
「番手=太さ」「スラッシュの数字=糸の構成」という基本を忘れず、たくさんの表記に触れながら慣れていきましょう。
知識があるだけで、生地選びの失敗も減り、より満足のいくものづくりや商品選定ができるようになります。
8. 番手と品質は比例する?誤解しやすいポイントを整理
糸の太さを表す「番手」という表記は、生地や衣服選びにおいてとても重要な指標です。しかし、この番手がそのまま「高級な生地」や「品質の高さ」と結びつくわけではありません。ここでは、よくある誤解と本当に見るべきポイントを整理していきます。番手が高いからといって、必ずしも優れた生地とは限らないことを、まずは知っておく必要があります。
8.1 番手が高い=高級生地?ではない理由
多くの人が陥りやすい誤解のひとつが、「番手が高い=高級=上質な生地」という思い込みです。確かに、100番手の糸は非常に細くて繊細であり、上質なドレスシャツなどにも使われることがあります。しかし、その一方で細い糸は切れやすく、耐久性が低いという特性も持っています。
たとえば、デニムなどに使われる10番手の糸は太くて頑丈なため、ラフな日常着として最適です。一方で、ワイシャツには80~100番手の細い糸がよく使われますが、これは見た目や肌触りを優先した結果です。用途によって「良い生地」の定義が変わるため、単純に番手の数値だけで良し悪しを判断してしまうのは危険です。
「高番手だから上質」ではなく、「用途に合っているかどうか」が本質的な評価ポイントになります。
8.2 糸の質・撚り・加工方法が品質を左右する
同じ番手の糸でも、品質には大きな差があります。その差を生み出す要素のひとつが原料となる繊維の質です。たとえば、30番手の糸であっても、超長綿やピマコットンなど上質な綿を使えば、光沢や肌触り、耐久性において大きな違いが出ます。
また、糸の撚り(より)も重要なポイントです。2本の糸を撚り合わせた双糸(そうし)は、同じ番手の単糸(たんし)に比べて強度が増し、仕上がりもなめらかになります。たとえば40番手の双糸(40/2)は、一本の40番手単糸よりもしっかりとした風合いがあり、高級Tシャツにもよく使われます。
さらに、強撚糸(糸を強く撚ったもの)はシャリ感のあるさらりとした風合いを持ち、甘撚糸は柔らかくふんわりとした仕上がりになります。このように、糸の質・撚り方・加工方法は、番手以上に最終的な生地の品質を大きく左右するのです。
8.3 消費者向け:番手よりも注目すべきチェックポイント
一般の消費者が「良い生地」を見極めるとき、番手の数字だけに注目するのは少し早計です。それよりも、以下のような複数のチェックポイントを意識することが、納得のいく買い物につながります。
1. 肌触り:手に取ったときのなめらかさや柔らかさを確認しましょう。特にシャツや肌着などは、肌に直接触れるものですので、触感は非常に大切です。
2. 生地の目の詰まり具合:細い番手でも織りが粗ければ透けやすくなります。逆に太い番手でも高密度に織られていれば、上質感や耐久性が高まります。
3. 糸構成(単糸 or 双糸):タグや製品説明に「30/2」「40/1」などと書かれていれば、それが糸の構成を示しています。双糸の方が丈夫で、洗濯にも強く、長持ちしやすい傾向があります。
4. 加工方法:シルケット加工、抗菌防臭加工など、糸や生地に施された加工にも注目してみてください。
番手はあくまで「糸の太さ」という物理的な数値でしかありません。その数字が意味することを理解したうえで、手触り、風合い、構造、加工など総合的に判断することが、賢い選び方になります。
8.4 まとめ
「番手が高い=良い生地」というイメージは、決して間違いではありませんが、すべてのケースに当てはまるわけではありません。用途や目的に応じた糸選びこそが、本当に「品質の高い製品」へとつながります。
糸の太さ(番手)だけに惑わされず、糸の種類・撚り・加工・構成までを総合的に見ること。これが、失敗しない生地・衣服選びのポイントです。
9. 番手・太さにまつわる素朴なQ&A
9.1 10番手と20番手、実際どれくらい違う?
糸の「番手(ばんて)」というのは、数字が小さいほど糸が太く、数字が大きくなるほど細くなるというルールで決まっています。つまり、10番手の糸は20番手よりもかなり太く、実際に触るとボリューム感や厚みがはっきりと違って感じられるのです。
たとえば、デニム生地は代表的な「10番手」使用の例です。しっかりとした厚みと丈夫さがあり、ゴツゴツした手触りになることが多いです。一方、「20番手」は、それよりも一段階細くて、カットソーやTシャツなどに使われることもあります。10番手と比べると、布地はやや軽く、柔らかく感じられます。
さらに興味深いのは、双糸(そうし)と呼ばれる2本撚りの糸です。たとえば「20/2」と表記されているものは、20番手の糸を2本撚り合わせた糸のことで、太さは理論的に10番手の単糸(20/1)とほぼ同じになります。つまり、糸の本数の組み合わせによっても、同じ番手でも厚みや強度が変化するというわけです。
このように10番手と20番手の違いは、数字以上に実用面での使用用途や質感に直結するため、商品選びのときに参考にする価値が大いにあります。
9.2 「細番手」とは具体的に何番手以上?
「細番手」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、アパレルや繊維業界では、特定の糸の細さを示す用語としてよく使われます。具体的には40番手以上の糸が一般的に「細番手」とされており、その上の60番手、80番手、100番手になると、非常に細い糸と評価されます。
たとえば、「80番手」や「100番手」の糸は高級ワイシャツなどによく使われており、しなやかで光沢のある美しい生地に仕上がるのが特徴です。逆に、16番手、20番手などは太番手の部類になり、カジュアルなTシャツや肌着などに適しています。
また、細番手の糸は耐久性が劣る傾向があるため、実際には双糸(そうし)にして強度を補っていることが多いです。たとえば「40/2」は40番手の糸を2本撚ったもので、厚みは20番手の単糸に近いですが、しなやかさや滑らかさは40番手そのままという優れた性質を持ちます。
このように「細番手」という言葉は、具体的な数字で見ると40番手以上を指していると考えるのが適切です。数字の感覚に慣れておくと、商品の選び方にも深みが出てきます。
9.3 番手表記のない服はどうやって厚さを見抜く?
お店でTシャツやシャツを見ていて、「この生地、どれくらいの厚さなんだろう?」と疑問に思った経験はありませんか?実は、すべての服に「20番手」や「30/2」などの番手表記があるわけではないため、番手が書かれていない服の厚さを見抜く方法を知っておくととても便利です。
まず基本的なのは透け感です。生地を光にかざしてみて手が透けるようなら40番手以上の細番手が使われている可能性が高く、しっかりと厚みを感じるなら20番手~16番手あたりの太番手が使用されていると推測できます。
また生地のドレープ(落ち感)にも注目です。細番手の糸で編まれた生地は滑らかで柔らかく、体に沿うように落ちる傾向があります。一方で太番手は、形を保ちやすく厚手で丈夫な印象があります。
さらに、生地の表面のざらつき感やハリ感もヒントになります。たとえば、デニムやヘビーオンスTシャツは番手が低く、糸が太いためざっくりした感触です。反対に、高級シャツやドレスシャツでは、きめ細やかでツルッとした手触りがあり、細番手が使われていると判断できます。
番手表記がないからといって諦める必要はありません。透け感・落ち感・肌触りといった感覚的な情報を組み合わせることで、糸の太さ=生地の厚みをかなりの精度で見抜くことができます。
10. まとめ:糸の太さ表記を知ることは素材選びの第一歩
糸の太さを表す「番手(ばんて)」は、服の着心地や耐久性、生地の風合いに直結する非常に重要な情報です。
例えば、1番手というのは非常に太い糸を指し、数字が大きくなるほど糸は細くなるという特性があります。
これは一般的な感覚とは逆で、知っていないと直感的に理解しにくい部分かもしれません。しかし、この逆転のルールを覚えることで、生地選びの失敗を防ぎ、自分に最適なTシャツやシャツなどを選びやすくなります。
たとえば、デニム生地には太めの10番手前後の糸が使われ、ワイシャツには非常に細い80番手〜100番手の糸が使われることが多いです。
このように、番手という情報だけで「薄手か厚手か」「しなやかかしっかりしているか」がある程度わかるため、素材選びの最初の判断材料として欠かせないのです。
10.1 今後の生地選びで番手をどう活用すべきか
今後、自分で生地を選ぶときや洋服を購入するときには、番手表記を一つの判断基準として活用しましょう。
たとえば、Tシャツに使われる糸は16〜40番手程度が多いですが、同じ番手でも糸の構成(単糸か双糸か)によって厚みや丈夫さが異なります。
「20/-天竺」などの表記は「20番手の単糸を使用した天竺編み」という意味で、/の前の数字が番手、後ろが糸の本数(構成)を示しています。
たとえば「30/2」とあれば、30番手の糸を2本撚って使っている「双糸(そうし)」です。この構成は丈夫さや生地の質感に大きく影響します。
同じ太さの番手でも、単糸(たんし)か双糸かで着用時のフィーリングはかなり違います。繰り返し洗濯しても伸びにくく、へたりにくい生地が欲しいなら双糸を選ぶのがポイントです。
このように、番手と糸構成をセットで覚えることで、自分が求めている用途にぴったりの生地を見極められるようになります。
10.2 番手を理解すると、Tシャツ選びも変わる
Tシャツ選びにおいても、番手の知識は大いに役立ちます。
たとえば、暑い季節にさらっと着られる軽やかなTシャツを探しているなら、30番手以上の細い糸で作られた生地を選ぶのが理想的です。
逆に、丈夫で厚手のTシャツを求めている場合には、16番手や20番手などの太い糸を使った製品がぴったりです。
特に「30/-」「20/2」などの表記がある場合、見た目が似ていても生地感や着心地に大きな差があるため注意が必要です。 「/」のあとの数字が1なら単糸、「2なら双糸」という違いがあるため、耐久性や風合いに影響します。
たとえば「20/-」は太めの単糸を使用しており、しっかりした厚みがあるのに対し、「40/2」は細い糸を2本使っていて、見た目は同じ厚みでも繊細でなめらかな肌触りです。
このような番手の知識があると、「なんとなく良さそう」で選んでいたTシャツ選びが、自分の好みや使用シーンに合わせて戦略的に選べるようになります。
これからTシャツを買う際は、タグや商品説明欄に書かれた「20/-」や「30/2」の表記にもぜひ注目してみてください。
番手と構成を知ることは、服をただ着るから“選んで着る”へステップアップする第一歩です。